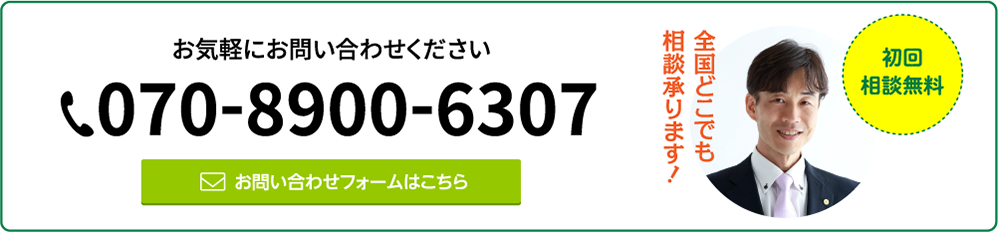ディライト社会保険労務士事務所のサポート内容
ディライト社会保険労務士事務所では以下のような人事・労務に関するお悩みごと、お困りごとをサポートしてまいります。
これ以外にも困ったらまずはディライト社会保険労務士事務所へご相談を!!
・労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、 厚生年金保険法に関する相談や各種届出
・社員の社会保険手続きや、労災保険の申請や育児介護休業給付申請など。
・就業規則および各種規程、各種協定の作成
・法定3帳票(労働者名簿・賃金台帳・出勤簿)+年次有給休暇管理簿の整備
・給与計算
・人事や労務に関する相談や、人事労務に関するリスク等のアドバイス
人事・労務以外のお悩みごと、お困りごともご相談ください。
・人財育成 ・能力開発 ・各種セミナーおよび勉強会
・採用関連 ・キャリアカウンセリング ・・・etc
・・・ものすごくざっくりサポート内容を記載しましたが、
もっと詳しく知りたい方は以下を参照ください。
社労士独占業務1号業務、2号業務、相談アドバイス3号業務およびその他業務を詳しく解説しております。
第1号業務:代理・代行業務(有償独占業務)
第1号業務:代理・代行業務(有償独占業務)
第1号業務とは、行政機関に提出する労働保険・社会保険の各諸法令に基づいて、
申請書等の作成および提出の代理または代行業務を行います。
また、労使間の紛争の代理人や行政機関に対する主張の代理人にもなれます。
具体的な業務としては以下のようなものが挙げられます。
・労働保険・社会保険の手続業務
労働基準法、労災保険法、雇用保険法、健康保険法、 厚生年金保険法、国民年金法等に基づく申請や届出などの代理または代行業務を行います。企業設立時の労働保険、社会保険適用に関する届出や労働者の入退社手続きや労働保険、社会保険の年度更新や算定基礎届。また労災保険の申請や育児介護休業給付申請など。煩雑な書類の作成および提出業務を社労士に任せることができます。
・介護保険の手続業務
介護保険に関する書類の作成および提出業務も社労士にて対応が可能です。3年に一度の法改正にて大きく制度が変わる介護保険。その都度、短期間での書類作成及び提出を保険者から求められます。また、毎年度提出が必要な処遇改善加算の計画書や報告書の作成も介護事業所の大きな負担となっています。このような書類の作成および提出業務についても社労士に任せることができます。
・助成金の申請等
助成金には雇用や人材の能力開発に関する助成金があり、一定の要件を満たすことで企業に助成金が支払われる魅力的な制度です。ただ魅力的な反面、要領把握の困難さ、また申請を行うまでの取り組みが煩雑で、申請を行う前に挫折してしまう話など耳にします。このような助成金申請等についても、申請書の作成および提出業務を社労士に任せることができます。
・年金の裁定請求書の作成・提出
各種年金(老齢・障害・遺族)の申請書の作成および提出も社労士に任せることができます。職員の年金相談は企業の担当者からもご相談いただきますが、実際の申請等の書類作成や提出業務は個人の方の依頼が多いかと思います。また年金の中でも障害年金は初診日要件、認定日要件、納付要件など専門的な知識が無い中で申請を行うには大変骨が折れます。知識が無い中での申請は、不支給につながることも多く、社労士を上手く活用することで、裁定結果が変わってくる場合もあります。
第2号業務:帳票作成業務(有償独占業務)
第2号業務:帳票作成業務(有償独占業務)
第2号業務とは、労働・社会保険の各諸法令に基づく帳簿書類の作成を行います。わかりやすく言うと、事業所で作成しておかなければならない書類を作成する業務です。 具体的には以下のような帳票作成を行います。
・就業規則および各種規程の作成
常時10人以上の従業員(パート含む)を使用する使用者は就業規則の作成、届出が義務づけられています。また従業員が10名未満の場合で就業規則の作成、届出義務が無い場合でも、それに代わる特定のルールを記載した規程等の作成が必要になる場合があります。このような就業規則や規程の作成について、モデルになる就業規則またサンプルがインターネット上に公開されており以前に比べると簡単に事業主や担当者でも作成を行うことができるようになりました。ただ、就業規則や規程は企業のルールブックです。モデル就業規則やサンプルをそのまま利用してしまうと、企業の実態にそぐわない、またトラブルが発生した際になんの役にも立たない、それどころか逆に、企業にとって不利な就業規則や規程となってしまう場合もあります。
このようなことが起きないように細心の注意を払い、就業規則や規程を作成していくことが重要なのですが、その為には膨大な時間と労力を要します。また専門的な知識を有するため、事業主や担当者が作成するにはかなり困難な作業と言えます。このように専門的知識を必要とする就業規則や各種規程の作成ですが、社労士に任せることができます。専門知識を有した社労士に作成を任せることで、企業の実態に即し、企業のリスクを軽減できる就業規則や規程を作成することができます。また就業規則や各種規程の作成および届出を有償で行えるのは社労士のみです。
・法定3帳票+年次有給休暇管理簿の整備
法定3帳票とは「労働者名簿」「賃金台帳」「出勤簿」を指し、この法定3帳票は労働基準法で労働者を雇用する事業主に対して整備し、保存することを義務付けています。また平成31年4月からは年次有給休暇管理簿の整備、保管も義務付けられ、法定4帳票とも呼ばれることがあります。法定4帳票の整備については、その必要となる項目も細かに定められており、法律に準拠した形式で帳票作成が必要となります。このような帳票の整備についても有償で行えるのは社労士のみです。
・各種協定の作成
労働者と雇用主の間で決められた約束事を書面にて契約した協定を労使協定といいます。協定書は一定のルールに乗っ取って作成及び締結が必要となり、事業主や担当者が作成を行うのはなかなか骨の折れる作業となります。また、協定書の内容では企業がリスクを負うような内容になってしまうこともあります。こちらも就業規則同様、専門知識を有した社労士に作成を任せることで、企業のリスクを軽減できる協定書の作成が行えます。この協定についても、作成等を有償でおこなえるのは社労士のみです。
第3号業務:相談アドバイス業務
第3号業務:相談アドバイス業務
第3号業務とは、人事や労務に関する相談や、人事労務に関するリスク等のアドバイスを行います。第3号業務における相談・アドバイス業務を適切に活用することで、企業の潜在的なリスクの軽減や健全な企業運営につながります。職員の退職、労使間トラブル、または各種法令違反などの企業に潜むリスクを第3号業務を通して未然に防ぐことが可能となります。
今日の企業経営はコンプライアンスや社会的責任の遵守が求められます。 これは大企業に限ったことではなく、個人事業、中小企業の経営もこの観点を持ち合わせなくては、今後の企業経営に支障をきたすことになります。健全な企業経営を行っていく上でも、第3業務の重要性はより重みを増しています。第1号業務及び第2号業務に比べ、目には見えにくい成果ではありますが、今後の企業経営において、第3号業務こそ社労士の専門性を活かした特に重要な業務であると考えられます。
具体的な相談やアドバイス内容は以下のように多岐にわたります。
・採用や退職、定年および解雇に関すること
・賃金や賞与および退職金の制度設計や適切な運用に関すること
・評価制度や昇給制度に関すること
・労働時間、休憩時間や残業についての労務管理に関すること
・年金や保険、および福利厚生に関すること
・職員の教育訓練や能力開発に関すること
・安全衛生管理、健康管理、メンタルヘルスに関すること
・ハラスメントに関すること
・個別労働関係紛争の事前防止や解決、紛争調整委員会におけるあっせん代理に関すること
特に今日は人の採用、育成、またそれに伴う評価および昇給の相談やアドバイスが多く、人を礎とする経営を目指す経営の一端を担うことも多くあります。
その他業務
その他業務:
社労士の業務にて第1号業務から第3号業務まで説明してまいりましたが、上記以外にも
・給与計算業務
・介護保険の代行申請
・公的年金の相談業務
なども社労士として対応できる業務です。
給与計算は税理士事務所でも行っているので、あえて社労士事務所で実施しなければならないということもありません。労働保険の年度更新、算定基礎届、随時改定などの社労士しか行えない業務と給与計算は密接に係るものが多くあるので、社労士に給与計算を依頼すれば、このような業務の対応がスムーズに行える、また対応の漏れを防ぐことが可能となります。ただし年末調整業務については税理士の独占業務となるため、社労士では対応が行えないため税理士との連携が必要となります。また企業向けでは無く、個人の方への対応が多くなりますが、介護保険の代行申請(要介護認定)や公的年金の相談なども社労士の専門分野となります。